皆さんこんにちは!GG加藤です!
今回は、「鳥居」について語っていこうと思います!
なんとなく、呼び名は知っているのですが、
どんな意味を持っているのか?
どのような役割なのか?
どのような成り立ちなのか?
なんのためにあるのか?
など、わからない事だらけだったので、
私なりに調べて見ました。
クエスチョン1 「鳥居」ってなんで「トリイ」?

神社に行くと一番最初現れる建築物
皆様ご存知の「鳥居」ですが、
まあ〜、神社のシンボル的、建築物ですよね。
どうして、鳥居って「トリイ」と呼ぶのでしょうか?
答えその1⇨
「鳥が、居易い」
・・・で鳥居と呼ばれるようになった
答えその2⇨「通り入る」
・・・でトリイ→鳥居になった
答えその3⇨
「色々あって分からない」(丸投げ!?)
これでは結局わかりませんね?
どうやら、様々な学説が説かれているようです。
そこもまた、興味深い!!
クエスチョン2 鳥居はいつ頃から作れられているのか?
では、そんな鳥居ですが、
いつからできたのでしょうか?
調べてみると
鳥居の起源とは、
答えその1
日本古来のモノであった説
( ^∀^)(ふむふむ納得)
答えその2
他国からのモノであった説
(;´д`)(え?違うの?)
答えその3 何だかよく分からない
Σ( ̄。 ̄ノ)ノ
(結局わからんのかい!!)
結論
「分からない」そうです。
学者の方がそう話していました。
そのよくわからない一説に、
答えその4⇨天照大神
(アマテラスオオミカミ)が、
天岩戸(あまのいわと)
に隠れた時、
大神のお出ましを願い、
長鳴鳥(ナガナキトリ)を、
横木にとまらせて、
鳴かせた
のが鳥居の起源である。とのこと。
ん・・・ってことは、つまり?
「鳥」や「とまり木」ってきたら、
ペット系?💡
この手のお話ですと、本業になりますので
軽く説明しますと、
長鳴鳥とはニワトリの事
しかしながら、一般の方のイメージする
ニワトリは、
白いボディーに、赤いトサカの鳥だと
思うのですが、
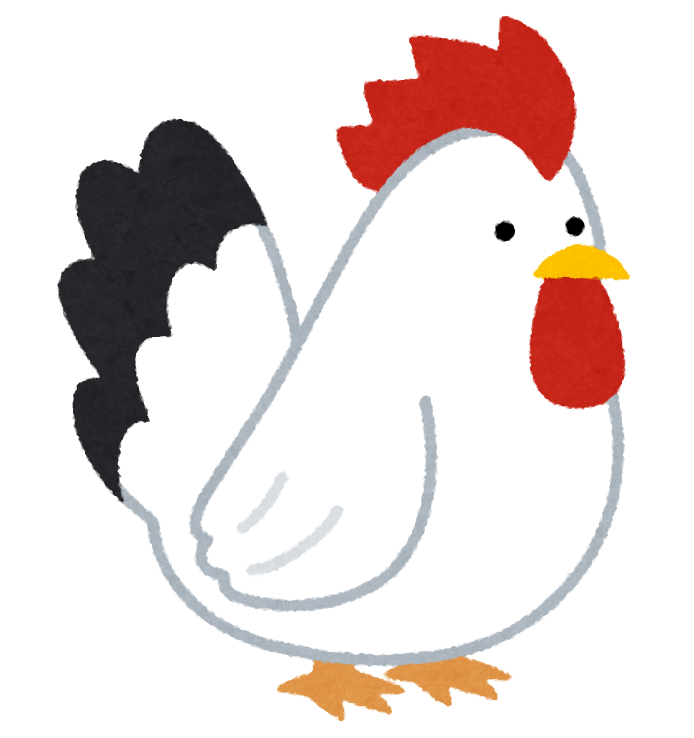
あれは、「コウニッシュ」
または、
「プリマスロック」
と言う外国のニワトリのことを指しています。
これらは、食肉用や卵用のニワトリとして
身近な存在です。
今回の長鳴鳥は、
日本国産のニワトリ。
しかも、
なが〜く鳴き続けるタイプ
新潟県原産の・・・
蜀鶏(とおまる)
秋田県の・・・
声良(こえよし)
高知県の・・・
東天紅(とうてんこう)
のようなニワトリの事を指しています。
話は戻りますが、
私は、ペットショップおじさんとして
この答え4の説が一番好きですね。
クエスチョン3 鳥居って何か決まり事があるのか?
鳥居の形は、色々ありますが
何か決まり事や様式は、あるのでしょうか?
調べてみると、
答え→決まり事は無いそうです。
様式として、大きく分けると
「神明系」と
「明神系」
の二つに分かれます。
なんと、漢字を入れ変えただけの違い?
私の理解としては、
神明系・・・
「地味で真っ直ぐ、真面目」
明神系・・・
「ハデ、反りの入った形」
「スタイリッシュ」
と言う感じ。
ちなみに、
必ずしも、一つの神社にある鳥居が
同じ様式で、
統一されているとは
限らない
との事。
また、同系統の鳥居同士を見比べても、
細部で異なることが多く、
同じものは無いのです。
鳥居こそが、八百万(やおよろず)の
様式があると言えるのでは無いでしょうか?
学者の方の受け売りではありますが、
実際に神社巡りをしていて、つくづくそう思いました。
クエスチョン4 どこからが神域?

鳥居を通った先が神域なのでは?
と私は思っていました。
ですが、大きい神社だと何個も
鳥居があったりします。
入り口から
「第1の鳥居」「第二の…」「第三の…」
と数えて行った時、
第1、第二の鳥居くらいまでは
出店が並んでいる
神社があったりしました。
「神域の中でお店開いて良いのだろうか?」
ふと、疑問に思ったこともありました。
よくよく、その出店の並んでいる手前の鳥居と、
拝殿前の鳥居を比べてみると違いが。
「しめ縄がない」
のです。
さらに言うと、
「神垂」(しで)と
呼ばれるものもありません。
この手に関する本を読んで、
学者さんのお話を伺い、
調べてみました。
どうやら、
「神域」とは、
鳥居に、しめ縄を飾った奥のことである。
と言うことでした。
鳥居は「玄関」「門」の意味合いがあり、
そこに「しめ縄」をすることで
神域の「結界」を作っている意味が
あるのだそうです。
そのため、
しめ縄のある鳥居の先には、
売店の類のものは一切ないそうです。
世俗の行動は一切取れないと言うことですね。
余談ですが、
今度神社巡りをしようと思っている
山形県鶴岡市にある「湯殿山神社」。
ここは、
「語るなかれ、聞くなかれ・・・」
と口外禁止の神社。
そのためか、本宮(ほんぐう)は
撮影禁止で
Youtube上もありませんでした。
それだけ、神域は大切で、
厳かな場であるということが伝わってきます。
是非とも、自分も見に行ってみたい!
そう思う今日この頃です。
今回のまとめ
と言うことで、今回は鳥居について
語ってみました。
鳥居一つとっても、歴史の深さや
趣の深さを感じさせられました。
そして、
その趣旨は「自由」であると
感じました。
ですが、
鳥居を通過する前と後では、
メリハリをしっかりとつけています。
自由の国、日本。
「自由な人生」のための「切り替え」。
日本人の心の形の一つかもしれません。
今回は、ここまで!
ありがとうございました。



コメント